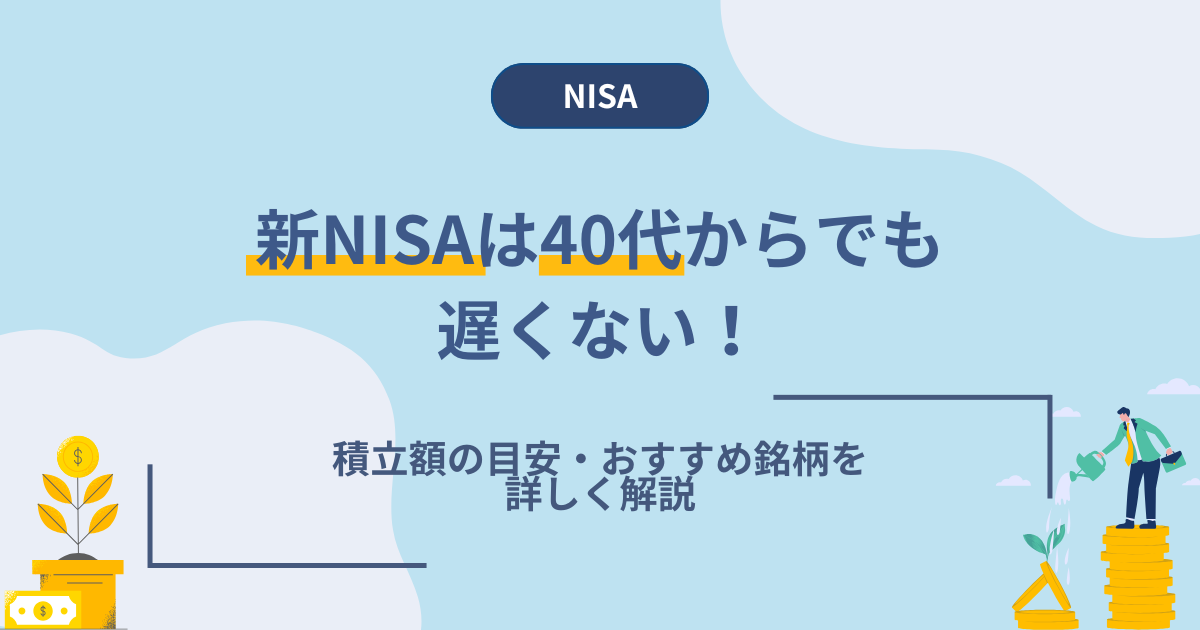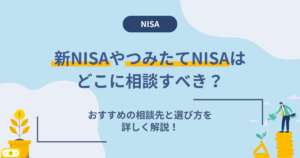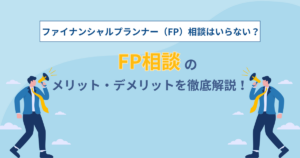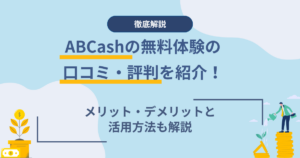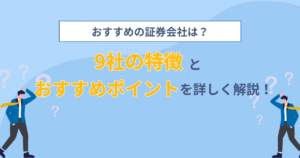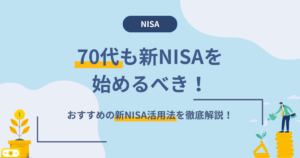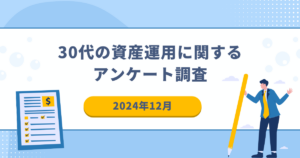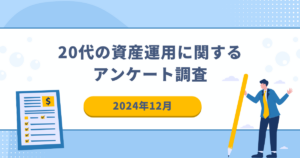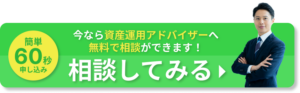- 40代におすすめの新NISA活用法を教えてほしい
- 新NISAで毎月いくら積立すればいいのか教えてほしい
- 新NISAで運用するときの注意点が知りたい
「40代からの資産形成、今から始めても間に合うの?」「老後資金のためにどれくらい積み立てればいいの?」そんな疑問を持つ人は多いだろう。
2024年から始まった新NISAは、非課税保有期間が無期限となり、年間投資枠も大幅に拡大した。この制度を活用すれば、40代からでも十分に資産を増やせる可能性が高い。
この記事では40代から新NISAを始めるべき理由や、毎月の積立額の目安、おすすめの投資商品まで詳しく解説する。
これを読めば、あなたも20年後、30年後に向けた資産形成をスタートできるはずだ。
40代から新NISAで運用を始めるべき理由

定年までの期間が近づいてきた40代。「もう投資を始めるには遅い」と思うかもしれないが、そんなことはない。
むしろ、40代だからこそ新NISAを活用した資産形成が有効な理由がある。詳しく見ていこう。
40代の新NISA利用状況|33.9%が利用中
金融庁の調査によれば、2024年9月末時点で40代のNISA口座保有数は4,826,897口座にのぼる。
総務省統計局の同月の40代人口約16,410,000人と比較すると、40代の33.9%がNISAを利用していることになる。
ちなみに、40代はもっとも口座数が多い年代だ。単純な人口比の問題もあるが、40代が資産形成の必要性を強く感じている証拠といえる。
同世代の3人に1人がすでに行動を起こしているので、まだの方は本記事を読んだらさっそくチャレンジしてみてほしい。
40代が新NISAで資産運用すべき理由とは?
40代が新NISAで資産運用を始めるべき理由は以下の3つだ。
- 子どもの教育・進学や住宅ローンの支払いに備えるため
- いわゆる「老後2,000万円問題」をクリアして老後資金を確保するため
- 非課税の恩恵を受けられる期間がまだまだ長いため
順に見ていこう。
子どもの教育・進学や住宅ローンの支払いに備えるため
40代は子どもの教育費や住宅ローンなど、大きな支出が続く時期だ。とくに以下のようなライフイベントへの備えが必要になるだろう。
- 子どもの高校・大学進学(入学金・授業料・仕送りなど)
- 住宅ローンの返済
- マイホームのリフォーム資金
- 親の介護費用
とくに住宅ローンが変動金利の場合、今後の金利上昇によって支払額が増える可能性がある。
たとえば残高2,000万円、残期間20年の住宅ローンの場合、金利が1%上昇すると月々の返済額は約9,000円増加する。年間で約11万円の負担増となる計算だ。
インフレ抑制のために日銀が年々政策金利を引き上げており、住宅ローンも影響を受ける可能性は決して低くない。
新NISAでの資産運用は、こうした予期せぬ支出増加に備える「貯蓄の目減り対策」としても有効だろう。
いわゆる「老後2,000万円問題」をクリアして老後資金を確保するため
金融庁の報告書で話題になった「老後2,000万円問題」。平均的な夫婦が老後30年間を過ごすには、公的年金に加えて約2,000万円の資産が必要とされている。
40代から65歳の定年までの期間は約20〜25年間だ。この期間を使って効率的に資産形成すれば、老後に必要な資金を貯めることは十分に可能だろう。
たとえば、月5万円を年利3%で20年間積み立てると、約1,640万円になる計算だ。
非課税で複利効果を最大限に活かせる新NISAは、40代からの老後資金形成に活用できるツールといえる。
非課税の恩恵を受けられる期間がまだまだ長いため
新NISAでは旧NISAの5年間という非課税期間の制限がなくなり、無期限で非課税メリットが得られるようになった。つまり40代からスタートしても、売却するまで一切の税金がかからない。
40代の場合、定年までの約20〜25年間、さらに老後の資産運用期間を含めると30年以上の長期投資が可能だ。
前述のとおり、たとえば月5万円を年利3%で20年間積み立てると、約1,640万円になる。
NISAではなく預金口座に預けておいた場合は、多少の利息はあるものの5万円×12ヶ月×20年で1,200万円のままだ。この差額を得るためにも、早めに取り組むべきだろう。
40代はまず新NISAのつみたて投資枠から始めよう

新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが用意されている。投資初心者の40代なら、まずはつみたて投資枠から始めるのがおすすめだ。
つみたて投資枠は年間120万円まで投資でき、長期・積立・分散投資に適した商品のみが対象となっている。
比較的リスクが抑えられた商品で、着実に資産形成を進められるのだ。つみたて投資枠のメリットは以下の3つ。
- 多くの証券会社で100円から気軽にスタートできる
- 「ドルコスト平均法」による安定運用が期待できる
- 手間やコストがかからない
それぞれのメリットを詳しく解説する。
多くの証券会社で100円から気軽にスタートできる
「投資は大きな金額が必要」というイメージを持つ人も多いが、実際はそんなことはない。
SBI証券や楽天証券など主要なネット証券では、つみたて投資枠でわずか100円から1円単位で積立額を設定できる。
また、積立日も給料日後など自分の生活リズムに合わせて選べるため、無理なく続けやすい。新NISAは、まさに「40代からの資産形成」の入口として最適なツールだ。
「ドルコスト平均法」による安定運用が期待できる
つみたて投資枠のもうひとつのメリットは、定期的に一定金額を投資する「ドルコスト平均法」を自然と実践できる点だ。この方法には以下のようなメリットがある。
- 市場が下落しているときに自動的に多く買える
- 価格の高い時期と安い時期の平均的な価格で投資できる
- 「いつ買うべきか」というタイミングを考える必要がない
- 感情に左右されず投資できる
たとえば相場が大きく落ちた2020年の「コロナショック」時に投資を始めた人でも、その後の相場回復で利益を得られた例が多い。
一方で、このときの下落で「損切り(売却)」をした人は、この利益は得られず損失だけが残ったままだ。
価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けられるドルコスト平均法は理にかなっている。つみたて投資枠なら勝手に実践できるので、さっそく試してみよう。
手間やコストがかからない
仕事や家庭で忙しい40代。資産運用にかけられる時間や労力は限られているだろう。
しかし、つみたて投資枠は一度設定すれば、あとは自動的に積立が続く仕組みだ。市場の動向をチェックしたり、売買のタイミングを見計らったりする必要がない。
さらに、つみたて投資枠で購入できる投資信託は販売手数料が無料で、信託報酬(運用管理費用)も低めに設定されている。
多くのコストがかかる「運用型の保険商品」などと比較して、最終的なリターンも大きくなりやすいのだ。
40代は新NISAで毎月いくら積み立てる?

新NISAで資産形成を始める際、「毎月いくら積み立てるべきか」は多くの40代が抱える疑問だ。
結論から言えば、無理のない範囲で続けられる金額を設定するべきだろう。以下で具体的な積立額の目安について解説する。
無理に投資に回すのはNG!余剰資金の範囲内で
投資は必ず収益が出るわけではなく、元本割れのリスクもある。そのため、生活に必要な資金や緊急時の備えを超えて無理に投資するのはおすすめできない。
必要以上に投資に回すと、以下のようなリスクがある。
- 急な出費に対応できず、投資中の資金を途中で引き出す事態に陥る
- 引き出しのタイミングが相場の下落時だと大きな損失を被る可能性がある
- 生活費を削りすぎて生活の質が低下する
- 精神的なストレスが増加し、長続きしない
とくに40代は教育費や住宅ローンなど固定費の負担が大きい時期。まずは3〜6ヶ月分の生活費を確保してから、余剰資金で投資を始めるのがおすすめだ。
金額別:平均年利3%で30年間運用したときのシミュレーション
では具体的に、毎月の積立額別にどれくらいの資産形成が期待できるのか、シミュレーションしてみよう。ここでは年利3%で30年間運用できた場合の最終的な資産額を見ていく。
| 毎月の積立額 | 累計投資額 | 30年後の資産額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 360万円 | 約583万円 | +約223万円 |
| 3万円 | 1,080万円 | 約1,748万円 | +約668万円 |
| 5万円 | 1,800万円 | 約2,914万円 | +約1,114万円 |
| 10万円 | 3,600万円 | 約5,828万円 | +約2,228万円 |
表からわかるように、毎月1万円の積立でも30年後には580万円以上になる可能性がある。また、5万円なら約2,900万円、10万円なら約5,800万円と、投資額以上の資産形成が期待できる。
40代から65歳の定年までは約20〜25年。この期間で考えると、月5万円の積立で約2,000万円程度の資産形成が見込めるため、老後2,000万円問題にも対策できるだろう。
自分の家計と老後の目標額に合わせて、無理のない範囲で積立額を設定するのがベストだ。
今すぐ大きな金額を用意できなくても、まずは少額からスタートし、収入アップや支出の見直しに合わせて徐々に増やしていく方法もある。
物価高で「お金の目減り」が起きる!少額からでも始めてみよう
2025年現在、日本ではインフレ傾向が続いている。2023年から2025年にかけて、年率2〜3%程度の物価上昇が続いているのだ。
これは単に「モノの値段が上がる」だけでなく、「現金の価値が目減りする」ことを意味する。
たとえば年率2%のインフレが続くと、100万円の預金は10年後には約82万円相当の価値になってしまう。何もしなければお金の価値は確実に減っていくのだ。
少額でも資産運用をスタートし、インフレ率を上回るリターンを目指せば、お金の実質的な価値を守りながら増やすことが可能になる。
まずは月々5,000円や1万円といった少額から始めて、値動きの雰囲気を実感してみるのもよいだろう。
40代からでも「少額・積立・長期」という投資の基本を守れば、物価高に対抗できる資産形成は十分に可能だ。
新NISA・つみたて投資枠におすすめの商品は?【40代向け】

40代が新NISAのつみたて投資枠で運用を始める際、どんな商品を選べばよいのだろうか。
ここでは、実際に40代に人気の高い投資信託ランキングを見ながら、おすすめの商品を紹介しよう。
| ファンド名 | 順位 | 委託会社 | 基準価額(円) | 純資産(億円) | 信託報酬(税込) | 100円投資の可否 | 運用実績(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・高配当株式・米国ファンド (四半期決算型) | 1位 | 楽天投信投資顧問 | 9,118 | 1,296.49 | 0.192% | 〇 | ー |
| eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 2位 | 三菱UFJアセット | 27,889 | 60,815.18 | 0.0814% | 〇 | 12.26% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 3位 | 三菱UFJアセット | 23,430 | 50,890.71 | 0.05775% | 〇 | 10.55% |
| 三菱UFJ純金ファンド | 4位 | 三菱UFJアセット | 35,921 | 3,777.23 | 0.99% | 〇 | 21.21% |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド (四半期決算型) | 5位 | 楽天投信投資顧問 | 9,706 | 49.95 | 0.297% | 〇 | ー |
| ゴールド・ファンド (為替ヘッジなし) | 6位 | 日興アセットマネジメント | 31,149 | 749.25 | 0.407% | 〇 | 21.39% |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100 インデックス・ファンド | 7位 | 楽天投信投資顧問 | 10,700 | 782.36 | 0.198% | 〇 | ー |
| iFreeNEXTFANG+インデックス | 8位 | 大和アセットマネジメント | 55,990 | 4769 | 0.7755% | 〇 | 28.23% |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド (四半期決算型) | 9位 | 楽天投信投資顧問 | 8,945 | 10.89 | 0.192% | 〇 | ー |
| 楽天・インド株Nifty50 インデックス・ファンド | 10位 | 楽天投信投資顧問 | 9,136 | 272.12 | 0.308% | 〇 | ー |
40代向けに特におすすめなのは、以下の点を押さえた商品だ。
- 信託報酬が0.3%以下と低コストで取引できる
- 世界分散型または米国株式中心で長期的な成長が期待できる
- 純資産総額が大きく流動性が高い
- 運用実績が安定している
ランキング上位の商品はこれらの条件を満たしており、40代からの長期投資に適しているといえる。
とくに「eMAXIS Slim」シリーズや「楽天・全米株式インデックス・ファンド」などは、低コストで分散投資ができる点が魅力だ。
元本割れのリスクを回避しながら、中長期的な資産形成を目指したい40代。ランキング上位の人気商品で投資を始めるのはおすすめの選択といえる。
まずはランキング上位の商品から、自分の投資方針に合ったものを選んでみよう。
40代は新NISAの成長投資枠も併用しよう!

つみたて投資枠での資産形成に慣れてきたら、成長投資枠の活用も検討してみよう。貯蓄にまだ余裕がある場合や、ボーナスなどの臨時収入があるときは、成長投資枠を併用するのがおすすめだ。
つみたて投資枠と成長投資枠の主な違いは以下のとおり。
| 比較項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 投資対象商品 | 金融庁が認定した投資信託中心の商品のみ | 投資信託、上場株式、ETF、REITなど幅広い商品 |
| 投資方法 | 積立投資が基本 | 一括投資、積立投資どちらも可能 |
| リスク | 比較的低~中程度 | 商品によってさまざま(高リスクも選択可能) |
以下では、成長投資枠の具体的なメリットやおすすめの活用法を解説していく。
成長投資枠のメリットとは?
成長投資枠のメリットは以下の3つがある。
- より幅広い金融商品から投資対象を選べる
- スポット投資・積立投資の両方に対応している
- 配当も非課税で受け取れる
これらはつみたて投資枠にはないメリットだ。順に詳しく解説する。
より幅広い金融商品から投資対象を選べる
成長投資枠の最大の魅力は、投資対象の幅広さだ。つみたて投資枠が金融庁認定の投資信託に限られるのに対し、成長投資枠では以下のような多様な商品に投資できる。
- 国内外の個別株式
- 国内外のETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
- アクティブ型の投資信託
- 高配当株
たとえば、特定の業界や成長企業に注目した投資や、高配当株を組み入れた配当狙いの投資戦略なども実現可能だ。より自分のスタイルに合った投資ができるだろう。
スポット投資・積立投資の両方に対応している
成長投資枠はボーナス時に一括投資するスポット投資も、毎月定額を積み立てる方法も選べる。たとえば以下のような活用法が考えられる。
- ボーナス月(6月・12月)に臨時ボーナス分を一括投資
- つみたて投資枠で毎月10万円投資しつつ、余力がある場合は成長投資枠でさらに5万円を積立
- つみたて投資枠で安定運用しながら、成長投資枠では多少リスクを取った株式投資
自分の収入パターンに合わせた柔軟な投資が可能だ。無理のない範囲で投資効果を高められるだろう。
配当も非課税で受け取れる
成長投資枠では、株式やETFからの配当金も非課税で受け取れる点も大きなメリットだ。通常、配当金には約20%の税金がかかるが、成長投資枠ではこれが免除される。
たとえば年間5万円の配当金を受け取る場合、通常なら約1万円が税金として差し引かれるが、成長投資枠なら5万円をそのまま受け取れるのだ。
この差額でさらに投資すれば、複利効果によって長期的には大きな差がつくだろう。
成長投資枠のおすすめ活用方法
成長投資枠のおすすめ活用パターンを3つ紹介する。
- つみたて投資枠と同じ銘柄を買い増してさらなるリターンを狙う
- 積立投資に慣れてきたら、個別株やアクティブに挑戦してみる
- 配当目当てで高配当銘柄の長期ホールドに活用する
リスクを抑えてリターンを増やすもよし、少しハイリスク・ハイリターンな戦略を取るのもよし。詳しく解説するので、自分のスタイルに合ったものを試してみてほしい。
つみたて投資枠と同じ銘柄を買い増してさらなるリターンを狙う
最も安全で効果的な成長投資枠の活用法のひとつは、すでにつみたて投資枠で購入している優良な投資信託を買い増すことだ。
この方法には以下のようなメリットがある。
- すでに理解している商品なので安心感がある
- 投資信託の選定に時間を使う必要がない
- 運用状況の管理が簡単になる
つみたて投資枠で成果が出ている銘柄なら、単純に買い増したぶんだけ期待できる利益が増える。複数の銘柄を管理する手間と知識も不要で、初心者におすすめの方法だ。
積立投資に慣れてきたら、個別株やアクティブに挑戦してみる
つみたて投資の知識や経験が蓄積されてきたら、成長投資枠では少し攻めの投資にチャレンジしてみるのもよいだろう。たとえば以下のような投資先が考えられる。
- 将来性が期待できる成長企業の株式
- 特定のテーマ(AI、再生可能エネルギー、ヘルスケアなど)に特化したETF
- 新興国市場に投資するファンド
- アクティブ運用の投資信託
全体の8割程度はインデックス型の投資信託で安定させつつ、2割程度を成長性の高い株式やアクティブ型の投資信託などに振り分ける戦略もおすすめだ。
安定性を保ちながらも、より高いリターンを狙えるだろう。
配当目当てで高配当銘柄の長期ホールドに活用する
40代からの資産形成では、将来の不労所得を意識した戦略もおすすめ。成長投資枠で高配当銘柄に投資して、できるだけ多くの分配金収入を非課税で受け取る戦略もアリだ。
高配当銘柄の例としては以下のようなものがある。
- 安定した業績を持つ大手銀行や電力・ガス会社の株式
- 高配当利回りのJ-REIT
- 米国高配当株式ETF
もちろん、配当だけでなく株価の値上がり益にも期待できる。とくに退職後の収入源として、非課税の配当収入は魅力的だ。余裕があればぜひ狙ってみよう。
40代が新NISAで運用するときの注意点

新NISAは優れた制度だが、利用する際にはいくつかの注意点もある。
- 損益通算や繰越控除はできない
- ハイリスク・ハイリターンの狙いすぎは危ない
- 焦ってNISA枠を使い切る必要はない
40代からの資産形成で損をしないために、これから解説する3つのポイントを押さえておこう。
損失もないものとして扱われる!損益通算や繰越控除はできない
NISAは利益に対する課税がない代わりに、損失も税制上「なかったこと」として扱われるのが特徴だ。つまり「損益通算」と「繰越控除」の制度が使えない。順に詳しく解説していく。
損益通算とは
損益通算とは、投資で生じた利益と損失を相殺する仕組みだ。NISA口座で損失が出ても、他の口座(特定口座など)の利益と相殺できない。
たとえば、A株で10万円の利益が出て、B株で15万円の損失が出た場合を見てみよう。
- 通常の特定口座
- 損失分(10万円―15万円=-5万円)を他の口座の利益から差し引ける
- NISA口座
- 損失分(-5万円)がなかったことになり、他の口座での利益から差し引けない
上記のような5万円程度の損失なら税金は微々たるものだが、仮にこの損失が100万円だったとしたら?特定口座なら他の口座の課税額を100万円分減らせるため、税金も20万円ほど下がる。
一方でNISA口座は損失がなかったことになり、他の口座の課税額は減らせない。つまり、20万円分損をしてしまうわけだ。
もちろん、NISA口座で利益が出て非課税の恩恵が受けられれば、損益通算で損をするリスクとは無縁だ。
慣れないうちは、あまり値動きが大きいリスキーな銘柄には手を出さないほうがよいだろう。
繰越控除とは
繰越控除とは、投資で生じた損失を最大3年間繰り越して、将来の利益と相殺できる制度だ。通常の特定口座では、たとえば今年発生した損失を、来年以降3年間の利益と相殺できる。
しかしNISA口座では繰越控除も適用されない。NISA口座で生じた損失は、将来に持ち越して税金を軽減するために使えないのだ。
そのため短期的な値動きを狙った取引や、高リスクな商品への投資は、損失が生じた場合のデメリットが大きくなる可能性がある。
NISA口座では、長期的な成長が期待できる銘柄に投資するのがおすすめだ。
「ハイリスク・ハイリターンの狙いすぎ」に注意!まずは人気の投資信託がおすすめ
40代からの資産形成では、残された時間が20〜25年程度と、20代や30代に比べると短い。
そのため「短期間で大きなリターンを得たい」という気持ちから、リスクの高い投資に手を出してしまう危険性がある。資産を増やすはずが、ほとんど失ってしまっては本末転倒だ。
まずは人気のインデックス型投資信託のように、低コストで分散投資ができる銘柄が40代の資産形成に適している。
ランキング上位の人気ファンドから始めて、投資経験を積んだ後にリスク許容度に応じて投資先を広げていく戦略を取ってみよう。
焦ってNISA枠を使い切らなくてOK!投資は「余剰資金」で
新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円と大きな非課税枠が用意されている。これを見て「枠を使い切らないともったいない」と考える人もいるかもしれない。
しかし、投資はあくまで余剰資金を使って取り組むべきものだ。無理に枠を使い切ろうとして、生活資金まで投資に回してしまうのは危険といえる。
非課税枠は毎年更新されるため、急いで今年の枠を使い切る必要はない。
40代は教育費や住宅ローンなど固定費の負担が大きい時期。とくに3~6ヶ月分の生活費と、直近3~5年程度の教育費や住宅関連費用は残して、余った分で投資に取り組むようにしよう。
40代で新NISAを始めるなら!悩んだときはプロに相談

資産運用を始めるにあたって「どの銘柄を選べばいいのか」「いくら積み立てるべきか」など、悩みは尽きないものだ。
とくに40代からのスタートでは、20代や30代と比べて、できるだけ短期間で利益が出る効率的な資産形成が必要になる。
そこで、証券会社やIFAのようなプロのアドバイスを受けながら、短期間での成功を目指すことも検討しよう。
以下では、プロに相談しつつ新NISAに取り組むメリットを解説する。
専門知識・経験を活かしたアドバイスで不安なく始められる
金融のプロは市場動向や商品に関する深い知識を持っている。プロのアドバイスを受けることで、以下のようなメリットが得られるだろう。
- 20~30年スパンでの投資に適した商品選定をサポートしてもらえる
- 投資初心者がよくやる失敗を避けられる
- 最新の税制や制度変更について調べなくても情報を得られる
とくに金融リテラシーに自信がない人や、投資がはじめてで不安を感じる人は、プロのアドバイスを受けることで安心感が段違いに上がるはずだ。
「目的・経済状況に合った資産配分」を教えてもらえる
資産運用で最も重要なのは、自分の目的やリスク許容度に合った「資産配分」だ。プロのアドバイザーは、以下のような観点から最適な資産配分を提案してくれる。
- 年齢や家族構成、収入状況
- 目標金額と投資期間
- リスク許容度
- 現在の金融資産の状況
- 将来の収入見通し
たとえば子どもの教育資金が必要な人、老後資金を貯めたい人、住宅ローン返済と並行して投資する人など、状況に応じて最適な戦略は異なる。
その点、プロは個別の事情を踏まえた、オーダーメイドの提案をしてくれるのだ。
銘柄リサーチなどの時間・手間をかけなくて済む
仕事や家事・教育で忙しい40代は、なかなか自分で投資商品を調査・分析する時間を確保できない。
プロは日々市場を分析し、膨大な情報から本当に必要な情報だけを厳選して提供してくれる。
定期的な運用状況のレビューや、必要に応じた投資配分の見直しも提案してくれるため、忙しい40代でも経済状況に合った効率的な資産運用が可能になるのだ。
自分に合ったアドバイザーを見つけて、40代からの資産形成を不安なく進めていこう。
新NISAは40代からこそ始めるべき!今日からでも遅くない資産形成を

40代からの新NISA活用は決して遅くない。むしろ、収入が安定し経済的な余裕が生まれる40代だからこそ、効果的に活用できる制度だ。
実に40代の約3人に1人にあたる33.9%がNISAを始めているので、この波に乗り遅れないようにしよう。
40代はまずつみたて投資枠からスタートし、余裕がある人やボーナスの一部を使える人は、成長投資枠で買い増しするとよい。
元本割れのリスクを抑えたまま、無理のない長期的な資産運用が可能になるはずだ。
「そうはいっても、不安で第一歩が踏み出せない」という人も多いだろう。事実、新NISAに限らず「投資」にはリスクがつきものだからだ。
そこで、証券会社やIFAのようなプロのアドバイスをもらいながら新NISAを始めるのもおすすめ。
損失を出したくない人や、決めている目標資産額をクリアするためのアドバイスがほしい人は、プロに相談して不安を解消してから新NISAを始めてみよう。