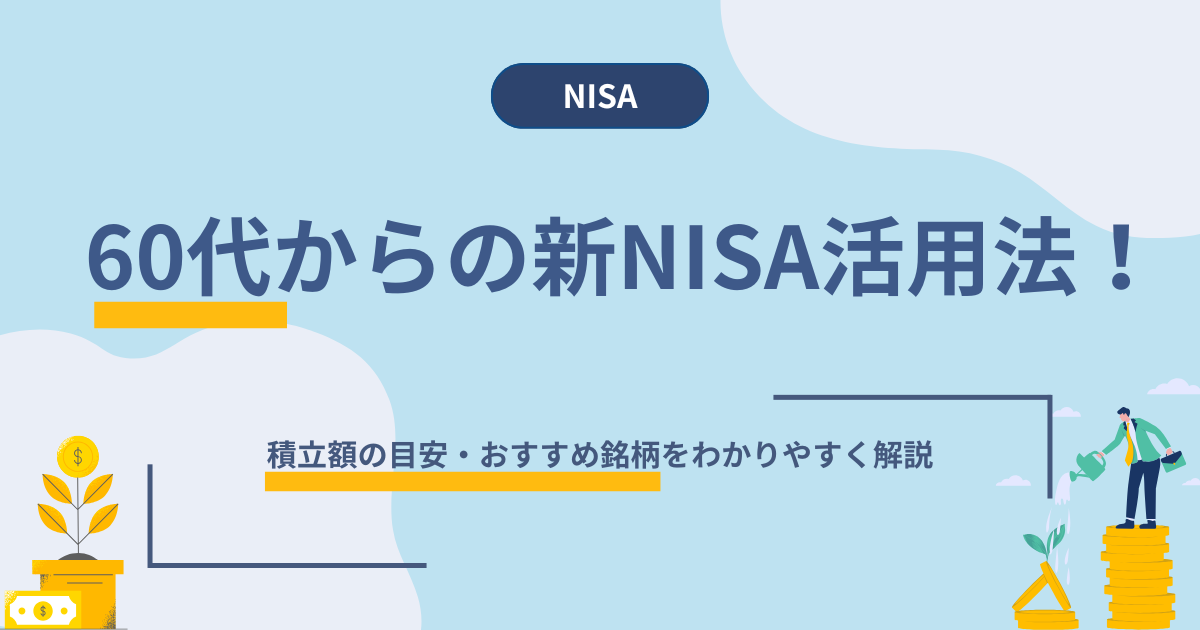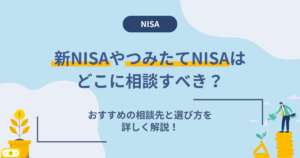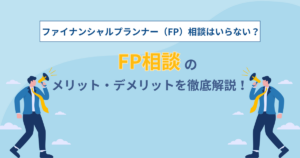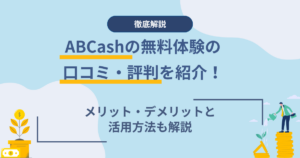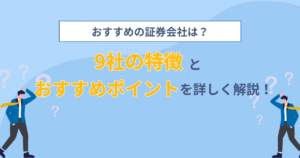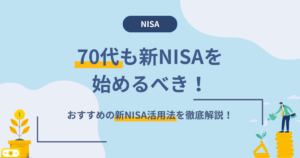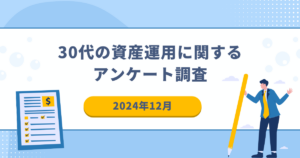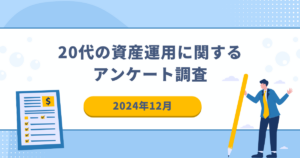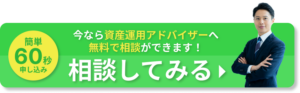- 60代におすすめの新NISA活用法を教えてほしい
- 新NISAで毎月いくら積立すればいいのか教えてほしい
- 新NISAで運用するときの注意点が知りたい
「退職金をただ預金していては目減りしてしまう」「老後の生活費に余裕を持ちたい」「子や孫に少しでも多くお金を遺してあげたい」
こうした悩みや願いを持つ60代は多いのではないだろうか。
長寿化が進む現代、60代からの人生はまだ20年以上続く可能性がある。物価上昇による資産の目減りを防ぎながら、安定した老後を過ごすためには、預金だけでなく資産運用も検討すべきだろう。
そして、この資産運用をサポートしてくれるのが、2024年からスタートした新NISAである。税金がかからない恩恵を受けながら、リスクを抑えた安全な投資で資産を育てられるのだ。
この記事では、60代からの資産防衛と形成に特化した新NISA活用法を詳しく解説する。
60代から新NISAで運用を始めるべき理由

「もう60代だから投資は遅い」と思っていないだろうか。
しかし、65歳の定年後も平均寿命まで約20年ある。その間の資金を守り増やすための手段として、新NISAは60代こそ活用すべき制度だ。
まずは60代の新NISA利用状況や、60代から資産運用すべき理由を見ていこう。
60代の新NISA利用状況|24.9%がNISA口座保有
金融庁が公表した最新データによれば、2024年9月末時点で60代のNISA口座数は約369万口座を突破している。
同時期の60代人口約1,483万人と照らし合わせると、実に4人に1人(24.9%)がすでにNISAを活用していることになる。
つまり60代の約4人に1人は、すでにNISAを始めていることになる。若い世代だけでなく、同世代の多くが老後に向けた資産形成・資産防衛策としてNISAを活用しているのだ。
60代が新NISAで資産運用すべき4つの理由
60代から新NISAを始めるべき理由は以下の4つだ。
- 「老後資金が底を尽きる」のを遅らせるため
- 子どもや孫へ相続する資産を形成するため
- 急な医療費や介護費の発生に備えるため
- 60代からでも新NISAの非課税効果が大きいため
詳しく見ていこう。
「老後資金が底を尽きる」のを遅らせるため
何もしなければ資産は減るだけだ。たとえば、2,000万円の貯蓄を取り崩しながら生活する場合、運用するかしないかで大きな差が生まれる。
| 年数 | 年利3%で運用しながら月7万円取り崩し | 運用せずに月7万円取り崩し |
|---|---|---|
| 5年後 | 約1,865万円 | 約1,580万円 |
| 10年後 | 約1,709万円 | 約1,160万円 |
| 15年後 | 約1,528万円 | 約740万円 |
| 20年後 | 約1,318万円 | 約320万円 |
| 23年後 | 約1,177万円 | 資金底尽き |
| 25年後 | 約1,075万円 | 資金底尽き |
| 30年後 | 約793万円 | 資金底尽き |
表からわかるように、運用しない場合は約23年で資金が底を尽きるのに対し、年利3%で運用できれば30年後でも約793万円が残る計算だ。
2023年の平均寿命は、男性が81.09歳、女性が87.14歳となっている。医療の進歩で、90歳以上まで生きる人も少なくない。
運用しながら貯蓄を取り崩すことで、充実した余生を過ごせる可能性は格段に上がるだろう。
子どもや孫へ相続する資産を形成するため
「子どもや孫の将来に少しでも役立つ資産を残したい」と考える60代も多いだろう。新NISAでは非課税で資産運用ができるため、相続財産の形成に最適だ。
たとえば、退職金の一部500万円を新NISAで運用した場合、年利3%なら15年後には約780万円に、20年後には約900万円に増える計算になる。
税金がかからないため、その分を含めて子や孫への相続資産として残せるのだ。
急な医療費や介護費の発生に備えるため
年齢を重ねると、自分や配偶者が急な病気やケガをするリスクも高まる。予期せぬ医療費や介護費用が必要になることもあるだろう。
健康保険や介護保険でカバーされない部分は自己負担となるため、いざというときの備えが必要だ。
とくに介護施設への入居費用は月々10〜20万円かかるケースも珍しくない。住み慣れた自宅での介護サービスを利用する場合でも、さまざまな費用が発生する。
新NISAで運用して資産を増やしておけば、こうした急な出費にも対応できる余裕が生まれるだろう。
60代からでも新NISAの非課税効果が大きいため
新NISAでは、運用益(値上がり益や配当金)に対する約20%の税金がかからない。この効果は運用期間が長いほど大きくなる。
たとえば、500万円を年利3%で15年間運用した場合を見てみよう。
| 項目 | 運用後の金額(概算) | 税金(約20.315%) | 実際の受取額 |
|---|---|---|---|
| 通常口座 | 約780万円 | 約50万円 | 約730万円 |
| 新NISA口座(非課税) | 約780万円 | 非課税 | 約780万円 |
約50万円もの差が生まれる計算だ。2024年までの「旧NISA」は非課税保有期間がわずか5年だったが、新NISAでは無期限になった。
60代からでも十分に非課税効果の恩恵を受けられるだろう。
60代はまず新NISAのつみたて投資枠から始めよう

新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがある。投資経験の少ない60代の方は、まずは簡単で手軽な「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめだ。
つみたて投資枠は、その名のとおり「つみたて」をする専用の投資枠。年間120万円まで投資でき、資産形成に適した商品だけが選べるようになっている。以下で詳しくメリットを見ていこう。
「月100円から」でもOK!気軽に始められる
つみたて投資枠の最大の魅力は、少額から始められる点だ。多くの証券会社では100円から積立投資が可能で、自分の余剰資金額に合わせて無理なく始められる。
たとえば毎月の年金受給額に少し余裕があるなら、その範囲内で1万円や3万円といった金額から始めることも可能だ。
突然の出費に備えて少額からスタートし、慣れてきたら金額を増やす柔軟な運用もできる。
日々の生活を圧迫せず「試しにやってみる」感覚で取り組めるのが、60代の投資初心者にとって大きなメリットだろう。
買える銘柄が厳選されている
つみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁が定める基準を満たした投資信託に限定されている。具体的には以下の条件を満たした商品だ。
- 販売手数料が無料
- 信託報酬(運用コスト)が一定水準以下
- 長期・積立・分散投資に適したファンド
60代は資産を減らすリスクに敏感な時期だろう。手数料などのコストが低い商品を選ぶことで、大切な老後資金の目減りを防ぎやすくなる。
つみたて投資枠ではこうした銘柄があらかじめ厳選されているため、あまり悩まずに商品を選べるのだ。
知識がなくてもカンタンに取り組める
つみたて投資のもうひとつの魅力は、一度設定してしまえば、あとは自動的に投資が続いていくこと。
毎月の年金受取日に合わせて自動で投資されるよう設定すれば、その後はとくに操作が必要ない。
「いつ買うべきか」「いつ売るべきか」という難しい判断をする必要もないため、投資の知識や経験がなくても始めやすい。
60代の投資初心者でも、月々の積立設定さえすれば、あとは自動的に資産形成が進む仕組みなのだ。
60代は新NISAで毎月いくら積み立てる?

新NISAを始めるとき、「毎月どのくらいの金額を積み立てるべきか」を決めるのが最初のハードルになるだろう。
適切な金額は個人の状況によって異なるが、いくつかの基準を紹介するので参考にしてみてほしい。
原則:生活に負担をかけないよう「余剰資金」で投資しよう
投資金額を考える際の基本原則は、生活に必要な資金を確保したうえで、余剰資金で投資することだ。
60代は現役時代と比べて収入が減少してしまうことが多いだろう。しかし、一方で医療費などの突発的な支出が増えるリスクがある時期だ。
まずは以下の資金を確保してから投資を考えよう。
- 生活資金(年金で足りない分を補う資金)
- 緊急用資金(突発的な医療費や修繕費などに備えた6ヶ月分の生活費)
- 余裕資金(趣味や旅行など生活を楽しむための資金)
これらを差し引いた後に残る資金が、投資に回せる「余剰資金」だ。身を削った無理な投資は負担になり、ストレスで長続きしない。自分の状況に合った無理のない金額を設定しよう。
新NISA運用シミュレーション|月3万円・5万円・10万円の3パターンを比較
では、具体的に毎月3万円、5万円、10万円を投資した場合、15年後にどれくらいの資産になるのかをシミュレーションしてみよう。
| 毎月の積立額 | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 累計投資額(15年) | 運用益(15年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万円 | 約195万円 | 約424万円 | 約693万円 | 540万円 | +約153万円 |
| 5万円 | 約326万円 | 約707万円 | 約1,156万円 | 900万円 | +約256万円 |
| 10万円 | 約652万円 | 約1,414万円 | 約2,312万円 | 1,800万円 | +約512万円 |
表からわかるように、毎月3万円の少額積立でも、15年後には153万円の運用益が期待できる。月5万円なら256万円、月10万円なら512万円と運用益はさらに大きくなる。
もちろん、これはあくまで年利3%で安定的に運用できた場合の試算だ。実際には市場の変動により結果は変わるため、これより高くなることも、逆に低くなることもあり得る。
ただし、多くの新NISA対象投資信託の平均リターンが3〜5%前後に収束しているので、参考値にはなるだろう。
まずは「100円から」でも気軽に始めてみよう
「いきなり大きな金額を投資するのは不安」という方は、まずは100円や1,000円といった少額から始めてみるのもよいだろう。
多くの人が投資に対して持つ不安は「投資の流れがわからない」「どのくらい損するかわからない」といったもの。
しかし100円からの投資なら、たとえ市場が下落しても損失は微々たるものだ。精神的な負担も少ないだろう。
少額での運用を数ヶ月続ければ、投資の基本的な流れや市場の動き方を確認できる。
その経験を踏まえて、徐々に投資金額を増やしていく方法をとれば、不安なく資産形成を進められるはずだ。
新NISA・つみたて投資枠におすすめの商品は?【60代向け】

60代が新NISAのつみたて投資枠で運用を始める際、どのような商品を選べばよいのだろうか。以下は、実際に60代に人気の高い投資信託ランキングだ。
| ファンド名 | 順位 | 委託会社 | 基準価額 (円) | 純資産 (億円) | 信託報酬 (税込) | 100円積立可 | 運用実績 (3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・高配当株式・米国ファンド (四半期決算型) | 1位 | 楽天投信投資顧問 | 9,118 | 1,296.49 | 0.192% | ○ | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 2位 | 三菱UFJアセットマネジメント | 23,430 | 50,890.71 | 0.05775% | ○ | 10.55% |
| 三菱UFJ純金ファンド | 3位 | 三菱UFJアセットマネジメント | 35,921 | 3,777.23 | 0.99% | ○ | 21.21% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4位 | 三菱UFJアセットマネジメント | 27,889 | 60,815.18 | 0.0814% | ○ | 12.26% |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド (四半期決算型) | 5位 | 楽天投信投資顧問 | 9,706 | 49.95 | 0.297% | ○ | — |
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 6位 | 日興アセットマネジメント | 31,149 | 749.25 | 0.407% | ○ | 21.39% |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100 インデックス・ファンド | 7位 | 楽天投信投資顧問 | 10,700 | 782.36 | 0.198% | ○ | — |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド (四半期決算型) | 8位 | 楽天投信投資顧問 | 8,945 | 10.89 | 0.192% | ○ | — |
| 楽天・プラス・S&P500 インデックス・ファンド | 9位 | 楽天投信投資顧問 | 12,413 | 4560.9 | 0.077% | ○ | — |
| 楽天・プラス・オール・カントリー 株式インデックス・ファンド | 10位 | 楽天投信投資顧問 | 12,086 | 3077.11 | 0.0561% | ○ | — |
このランキングから読み取れる60代の特徴が何点かある。
まず、1位・5位・8位の「高配当株式」ファンドが高い人気を集めていることだ。定期的な分配金で、資金を取り崩さずに老後の生活資金を補いたいニーズがあるのだろう。
また、3位の「純金ファンド」や6位の「ゴールド・ファンド」が上位にランクインしているのも特徴。
金は資産防衛の手段としての知名度が高いことから、インフレに強い資産として60代に選ばれているようだ。
そして、2位・4位・9位・10位のように、他の年代でもよく選ばれる低コストのインデックスファンドも多くランクインしている。
60代でも、長期的な成長性と安定性がある投資先として人気が高い。
これらのことから、60代にとくにおすすめなのは以下の点を押さえた商品だ。
- 信託報酬が低く、長期保有に適している
- 分配金が期待できる高配当銘柄が含まれている
- 世界分散型で、1つのファンドでリスク分散ができる
- インフレに対応できる実物資産(金など)が含まれている
とはいえ、まずはランキング上位の商品から始めても問題ない。気になる銘柄に少額からでも投資してみよう。
60代は新NISAの成長投資枠も併用しよう!

つみたて投資枠での運用に慣れ、投資の基本を理解したら、余裕資金を成長投資枠で運用することも視野に入れてみよう。
とくに退職金や臨時収入など、まとまった資金が用意できるときは、成長投資枠の併用で資産形成の効果を高められる可能性がある。
なお、新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の主な違いは以下のとおりだ。
| 比較項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円(毎月10万円) | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 投資対象商品 | 金融庁が認定した投資信託中心の商品のみ | 投資信託・上場株式・ETF・REITなど選択肢が豊富 |
| 投資方法 | 積立投資のみ | 一括投資・積立投資の両方に対応 |
| リスク | 低め~中程度が多い | 低め~高いものまでさまざま |
以下で、詳しい成長投資枠ならではのメリットや、おすすめの活用方法を解説する。
成長投資枠の3つのメリット
成長投資枠には60代にとって魅力的なメリットが3つある。
- 配当金も非課税で受け取れる
- 積立投資とスポット(一括)投資の両方に対応している
- より多様な金融商品から選べる
配当金が非課税になれば、年金を補う収入源として効率的に活用できる。たとえば年間20万円の配当なら通常約4万円の税金がかかるところ、成長投資枠なら全額が手元に残る。
また、月々の積立だけでなく、必要に応じて一括資金投入も可能なので柔軟な運用ができる。退職金などのまとまったお金を運用するのにも最適だ。
そして、つみたて投資枠よりも幅広い投資対象があるのもポイント。この幅広い投資対象を活かした活用方法を次で見ていこう。
60代の成長投資枠おすすめ活用方法2選
60代から成長投資枠を活用するなら、以下2つの方法がおすすめだ。
- つみたて投資枠にはない「値動きの大きい銘柄」にチャレンジしてみる
- つみたて投資枠と同じ銘柄を買い増しする
以下で詳しく見ていこう。
つみたて投資枠にはない「値動きの大きい銘柄」にチャレンジしてみる
前提として、老後資金の大半は安全性の高い商品で運用すべきだ。しかし一方で、余裕資金があれば「攻めの投資」に回すのもよいだろう。
成長投資枠では、つみたて投資枠で買えない以下のような商品も選べるからだ。
- 高配当の優良企業株
- 電力・通信・医薬品などの分野を主とする、安定した配当が期待できる個別株
- アクティブ運用の投資信託
- プロが銘柄選定する「ハイリスク・ハイリターン」寄りな成長志向の投資信託
- 特定テーマのETF
- 医療やIT・AI技術革新など成長分野に特化した上場企業の投資信託
ただし、こうした商品への投資はリスクも高まることを忘れてはならない。全体の資産のうち10~20%程度に抑えるなど、リスクコントロールの意識が60代にはとくに重要だ。
つみたて投資枠と同じ銘柄を買い増しする
よりリスクを抑えた方法としては、つみたて投資枠ですでに買っている投資信託を成長投資枠でも買い増す選択肢がある。この方法のメリットは以下のとおりだ。
- 馴染みのある商品なら安心して投資を続けられる
- 分散投資の効果を維持したままリターンを増やせる
- 運用状況の管理が一元化できる
すでにリターンが出ている投資信託ならリスクも限られる。新たな銘柄選びの手間をかけず、非課税枠を最大限に活用できるだろう。
成長投資枠の運用シミュレーション|毎月20万円積立したらどうなる?
成長投資枠では年間240万円の投資が可能。月で割ると、1ヶ月あたり最大20万円の積立が可能だ。
もし、つみたて投資枠10万円とは別で、成長投資枠に毎月20万円を積立していった場合、どのように資産が増えていくかシミュレーションしてみよう。
つみたて投資枠と同じ商品を年利3%で15年間運用した場合
まずは、安定感のある「毎月10万円を年利3%で運用しているつみたて投資枠と同じ商品を、成長投資枠でも毎月20万円買い増しした場合」を見てみよう。
以下は成長投資枠における投資額と資産額の推移だ。
| 経過年数 | 資産額 | 累計投資額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年後 | 約1,304万円 | 1,200万円 | 約104万円 |
| 10年後 | 約2,828万円 | 2,400万円 | 約428万円 |
| 15年後 | 約4,625万円 | 3,600万円 | 約1,025万円 |
つみたて投資枠の分を合わせると、15年後には約6,937万円(運用益約1,537万円)の資産形成が期待できる。累計投資額5,400万円に対し、28%も資産額が増える計算となった。
アクティブ運用の商品を平均年利5%で15年間運用できた場合
成長投資枠でリスクを取ったアクティブ運用に挑戦し、年利5%を達成できた場合のシミュレーションを見てみよう。以下が、成長投資枠における投資額と資産額の推移である。
| 経過年数 | 資産額 | 累計投資額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年後 | 約1,406万円 | 1,200万円 | 約206万円 |
| 10年後 | 約3,302万円 | 2,400万円 | 約902万円 |
| 15年後 | 約5,869万円 | 3,600万円 | 約2,269万円 |
15年後には約5,869万円の資産形成が期待できる。年利3%の場合と比べて約1,244万円もの差が生まれる計算だ。
なお、年利3%で運用しているつみたて投資枠の分と合わせると、累計投資額5,400万円に対し50%以上も資産が増えることになる。
ただし、アクティブ運用は必ずしも高いリターンを保証するものではない。むしろ市場平均を下回るリスクも少なくないのだ。
老後資金を潰してしまうことだけは絶対に避けなければいけないため、「あくまで余剰資金で投資する」原則を徹底しよう。
60代が新NISAで運用するときの注意点

60代は資産を減らすリスクをなるべく避けるべき時期だ。新NISAは優れた制度だが、以下で解説するポイントはしっかり理解しておこう。
「損益通算」と「繰越控除」はできないので注意
NISAは利益に対する課税がない代わりに、損失も税制上なかったこととして扱われる。つまりNISA口座で損失が出ても、他の口座(特定口座など)の利益と相殺する「損益通算」ができない。
たとえばNISA口座または特定口座で運用するA株に10万円の損失が出て、特定口座でB株に15万円の利益が出た場合は、以下のようになってしまうのだ。
- パターン①A株の運用口座が特定口座の場合
- 差し引き5万円の利益に対してのみ課税
- パターン②A株の運用口座がNISA口座の場合
- 特定口座の15万円全額に課税されてしまう
税率はおよそ20%となるので、パターン②の場合は2万円ほど損をしてしまう計算になる。
また、今年の損失を翌年以降3年間の利益と相殺できる「繰越控除」もNISA口座では適用されない。
仮に特定口座で100万円の損失が出た場合、むこう3年分の利益から差し引いて課税額を減らすことが可能だ。
しかし、NISA口座にはそれがないため、むこう3年分の利益にまるごと課税されてしまう。
「損益通算」と「繰越控除」が使えないことから、NISA口座は「できるだけ値動きが激しすぎない商品」を運用するのがよいだろう。
リスクを取りすぎて老後資金を潰さないように注意
60代が注意すべきは「老後資金をリスクの高い投資で失ってしまう」ことだ。若い世代と違い、大きな損失を働いて取り戻す余裕がないことを忘れないようにしよう。
たとえば2008年のリーマンショックでは、世界の株式市場が一時的に50%以上も下落した。
高いリターンを求めて値動きが激しい株に投資しているときに大暴落が起きれば、老後資金が大幅に目減りしてしまう。
60代の投資では以下のような点に注意して、リスクを適切にコントロールしてほしい。
- 投資の大半を安定性の高いインデックス型投資信託などに配分する
- 高リスクな商品への投資は全体の10%程度に抑える
- 急激な相場変動時にも慌てて売却しなくて済む余裕資金を持っておく
投資は「元本割れ」のリスクがあることを常に念頭に置き、無理のない範囲で行うことが老後資金を蓄える60代にはとくに重要だ。
無理をしてNISA枠を埋めようとしないように注意
新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円と大きな非課税枠が用意されている。そのため、「枠を使い切らないともったいない」と考えがちだ。
しかし60代は年金や貯蓄からの余裕資金の範囲内で投資し、生活資金や緊急用資金を確保することを優先しよう。
NISA枠を埋めることが目的になり、本来使うべきではない生活資金まで投資に回してしまうのは非常にリスキーだ。
非課税枠は毎年更新されるため、必ずしも今年の枠を使い切らなくてもよい。無理のない範囲で活用しよう。
60代で新NISAを始めるなら!悩んだときはプロに相談

新NISAへの投資を始める際には、多くの疑問や不安が生じるものだ。
「老後資金を減らさないためにどう管理すべきか」「退職金からいくら積立するのが適切か」「相続を考えた運用はどうすればよいのか」など、60代特有の悩みも多いだろう。
とくに60代は年齢的に「失敗できない」プレッシャーも大きいはず。そんなときは、プロのアドバイザーへの相談も検討してみよう。
「どうやって始めるか分からない」不安はプロに解消してもらおう
投資の初心者にとって、口座開設の手続きや銘柄選びなど、始めるまでのハードルは意外と高い。とくにオンラインでの手続きに不慣れな方は、より不安を感じやすいだろう。
そこでプロのアドバイザーに相談すれば、以下のような点でサポートを受けられる。
- 口座開設の手続き方法の説明や代行
- 自分の状況に合った投資プランの提案
- 初心者にもわかりやすい銘柄選定のアドバイス
- 不安や疑問点への回答
「投資は難しそう」という先入観から一歩を踏み出せないでいる方は、まずは証券会社やIFA(投資アドバイザー)などに相談だけでもしてみるのがおすすめだ。
プロは「リスク管理」の専門家!最適な資産配分のアドバイスをもらおう
ここまで何度も触れてきたように、60代の資産運用は「リスクコントロール」が最重要だ。
プロのアドバイザーは、あなたの状況に合わせた最適な資産配分を提案してくれる。以下のような観点からアドバイスをもらえるだろう。
- 年齢や家族構成、健康状態に合わせたリスク許容度の診断
- 老後資金全体における投資資金の適切な割合
- 投資信託・株式・債券・不動産などへの資産の分散方法
- 相場急変時の対応ポイントや見直しのタイミング
自分では気づかないリスクをプロの目線で指摘してもらえれば、不安なく資産運用に取り組めるはずだ。
「仕事がまだ忙しい」人もプロの手を借りれば手軽にスタートできる
60代と一口に言っても、まだ現役で働いている方も多い。とくにセミリタイア中でまだ仕事をしている60代や、老親の介護などで忙しい方は、投資の勉強や市場分析に時間を割けないケースも多いだろう。
そこでプロのアドバイザーに相談すれば、以下のように「手間や時間をかけずに済む」メリットが得られる。
- 自分で調べる時間を大幅に節約できる
- 市場動向を常に追う必要がない
- 投資判断を任せられるので定期的なチェックの手間が省ける
自分の時間を大切にしながら資産運用を始めたい方は、プロの力を借りることも考えてみよう。
新NISAは60代からでもメリットが大きい!老後資金を守り育てよう

60代は資産を「守りながら育てる」時期。老後資金が底をつくのを遅らせ、子どもや孫への相続資産を形成しなければならない。
将来、突然発生する可能性がある医療費や介護費にも対策する必要がある。新NISAはそれに最適な制度だ。
まずはつみたて投資枠で少額からスタートし、慣れてきたら成長投資枠も併用する段階的な進め方がおすすめ。
つみたて投資枠ならリスクを抑えた商品が厳選されており、60代の投資初心者でも安心して始められる。
ただし、投資には当然「元本割れ」のリスクが伴う点に注意。不安を感じるなら、プロのアドバイザーに相談するのもおすすめだ。
自分の状況に合った投資プランを組んでもらえれば、安心して資産形成を始められる。プロのアドバイザーの多くは無料で相談できるので、まずは気軽に悩みや目標を話してみよう。