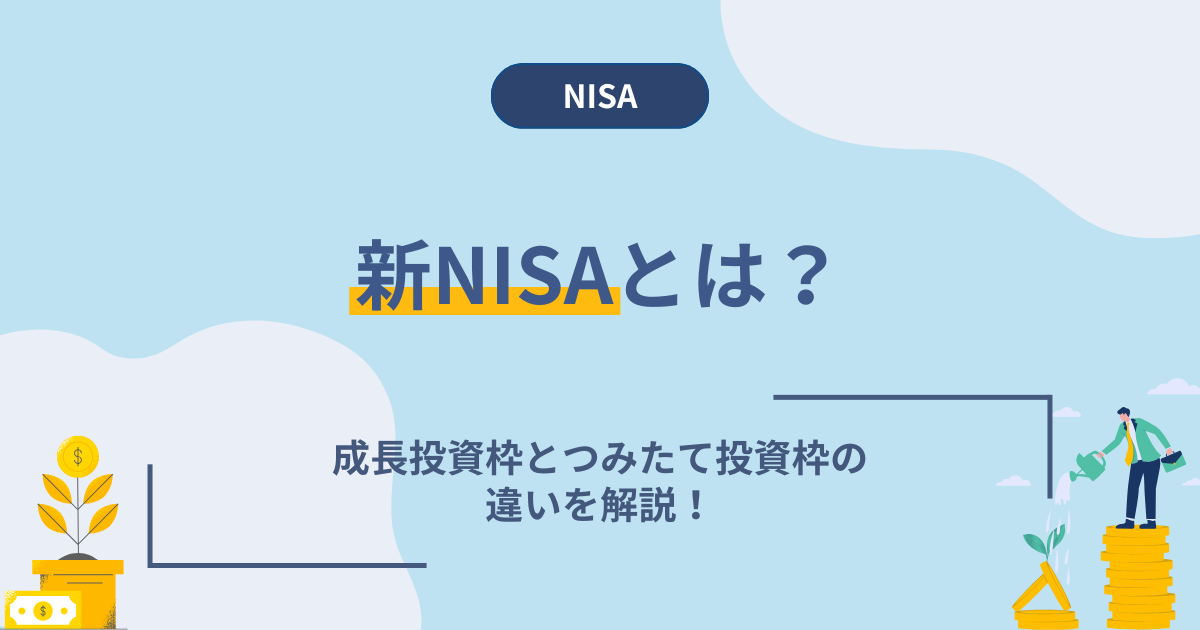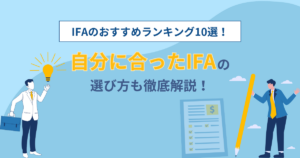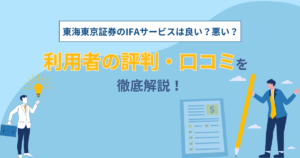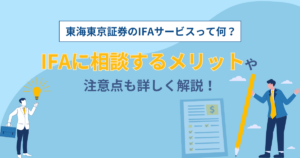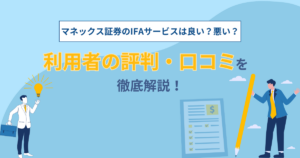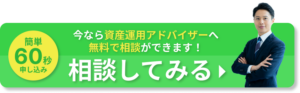- 旧制度から新NISAへの移行で何が変わったのか知りたい
- 新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の違いが知りたい
- 新NISAは成長投資枠とつみたて投資枠どちらを使うべきか知りたい
2024年1月に一般NISA・つみたてNISAから生まれ変わった新NISA。制度がガラリと変わったため、両者の違いが分からずに悩んでいる方も多いのではないだろうか。
旧制度を引き継ぐ枠ではあるが、明確に違う点もあるので始める前に違いや特徴を把握しておきたい。
本記事では新NISAの概要や枠の特徴の違い、メリット・デメリット、どちらを選択するべきかの考え方などを解説する。
相談先として資産運用ナビの魅力も紹介するので、新NISAの枠の使い方に悩んでいる人はぜひ参考にしていただきたい。
新NISAとは?

新NISAとは、株式や投資信託などの投資で得た利益が非課税になる個人投資家向けの税制優遇制度だ。
NISAは「Nippon Individual Savings Account(少額投資非課税制度)」の略で、2024年1月に旧NISAから改正された。
本章では、NISAのメリットや旧NISAからの変更点について詳しく解説する。
それぞれの内容について、以下で順番に見ていこう。
NISAのメリット
NISAにおける最大のメリットは、投資で得た利益に対して税金がかからないことだ。
たとえば、投資元本100万円に対して50万円の利益が出た場合、通常は利益に対して20.315%の税金(約10万円)が発生する。
しかし、NISA口座を利用すれば利益が非課税になり、50万円の利益がそのまま手元に残るのだ。
NISAは、投資を効率的に行って利益を最大化できる有効な税制優遇制度だと認識しておこう。
旧NISAからの変更点
旧NISAから新NISAへの変更点は、以下のとおりだ。
| 新NISA | 旧NISA | |||
|---|---|---|---|---|
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | 一般NISA | つみたてNISA | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 | 5年 | 20年 |
| 投資可能期間 | 2024年から恒久化 | 2024年から恒久化 | 2023年まで | 2023年まで |
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 | 120万円 | 40万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | ― | ― | |
| 1,200万円(内数) | 1,800万円 | |||
| 投資対象商品 | 株式・投資信託 | 一部の投資信託 | 株式・投資信託 | 一部の投資信託 |
| 購入方法 | 積立・一括 | 積立 | 積立・一括 | 積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||
| 併用 | 成長投資枠とつみたて投資枠を併用可 | 一般NISAとつみたてNISAの併用不可 | ||
改良された点として、新NISAでは非課税保有期間が無制限になり年間投資枠が拡充されたことが挙げられる。
また、旧NISAでは一般NISAとつみたてNISAのどちらかしか選択できなかったが、新NISAでは2つの投資枠を1人で利用可能だ。
年間投資額が2つの投資枠を合わせて360万円のため、目的に応じて柔軟な投資が可能だ。
まずは、新NISAに関するこれらの基本情報をぜひ押さえておこう。
新NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の違い

成長投資枠・つみたて投資枠とは、新NISA制度で用意されている2つの投資枠だ。
しかし、これらの具体的な違いがわからず投資に踏み切れていない方もいるだろう。
本章では、2つの投資枠に関する以下の違いについて詳しく解説する。
- 年間投資枠
- 非課税保有限度額
- 投資対象商品
- 購入方法
これらの違いを知ることで新NISAの全体像を理解でき、自分に適した投資を実行可能だ。
それぞれの違いの詳細について、以下で順番に見ていこう。
年間投資枠
2つの投資枠の違いの一つに、年間投資枠が挙げられる。
年間投資枠とは、NISA口座において非課税で投資できる年間の上限金額のことだ。
具体的には、以下のような違いがある。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
つみたて投資枠の年間投資枠が120万円で設定されている一方で、成長投資枠では2倍の240万円なのが特徴だ。
余剰資金の投資用や毎月の積立用など、用途に応じて使い分けするのがおすすめといえる。
無理のない範囲でNISA制度を有効に活用しよう。
非課税保有限度額
成長投資枠とつみたて投資枠においては、非課税保有限度額にも違いが見られる。
非課税保有限度額とは、NISA口座で保有できる金額の上限のことだ。
具体的な違いとしては、以下の内容が挙げられる。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | |
| 1,200万円(内数) | 1,800万円 | |
このように、つみたて投資枠は1,800万円の限度額を使い切れる一方で、成長投資枠においては1,200万円までと制限付きなのが特徴だ。
成長投資枠は年間240万円の投資が可能なため、最短で5年間の投資をすれば1,200万円分まで枠を埋められることを意味する。
2つの投資枠の非課税保有限度額については、ベテラン投資家でも勘違いしている方も多い。
金融庁のNISA特設サイト「よくある質問」でこれらの内容に関するQAが掲載されているため、こちらもぜひ参考にしよう。
投資対象商品
2つの投資枠では、投資対象商品も異なる。
具体的な違いは以下のとおりだ。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資対象商品 | 株式・投資信託 | 一部の投資信託 |
成長投資枠では、国内・海外の株式や投資信託などから幅広く投資商品を選択できる。
一方、つみたて投資枠では金融庁が定める基準を満たした投資信託の銘柄に厳選されているのが特徴だ。
投資対象商品の違いを把握し、適切な投資枠を利用しよう。
購入方法
2つの投資枠では購入方法が異なるのも特徴だ。
具体的には、以下のような違いがある。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 購入方法 | 積立・一括 | 積立 |
成長投資枠では毎月一定の金額で購入しても良いし、まとまった資金で一括購入しても問題ない。自分の好きなタイミング・金額で購入できるということだ。
一方、つみたて投資枠では毎月積立など定期的に投資商品を購入するスタイルになっており、購入タイミングで悩まなくていいのが魅力といえる。
これらの違いを把握し、自分の目的や希望に応じて2つの投資枠を使い分けしよう。
新NISAの成長投資枠のメリット・デメリット

新NISAの2つの枠を使い分けるには、それぞれのメリットとデメリットを把握しておくことが大切になる。
ここからは、「成長投資枠」を活用することのメリットとデメリットをそれぞれ解説する。
まず、メリットを抜粋すると、以下の3つが挙げられる。
- 投資対象商品の幅広さ
- スポットで買付ができる
- 年間投資額が大きい
上場している個別株式が対象に含まれるのが大きな特徴だ。
投資信託よりも値上がりする銘柄を見極める必要があるなど、企業の業績やチャートを読む能力が要求されるが、成長する銘柄にうまく投資できれば大きな値上がりが期待できる。
また、毎月一定額を積み立てるだけでなく、スポット購入も可能だ。
年間投資額も240万円もあるため、短期間で資産形成を進めたい人に向いている。
一方、以下のようなデメリットもある点には注意されたい。
- 投資知識が必要
- 運用の手間がかかる
個別株式は、さまざまな株式や債券に分散投資できる投資信託と比較して、値動きは大きくなりやすい。
業績によって大きく株価が上昇する可能性がある一方で大きく値下がりするリスクもあり、株価の上昇を捉えるにはチャート分析したり企業の業績をチェックしたりする知識が求められる。
積立投資と比較して運用の手間や時間がかかる点もデメリットだ。
新NISAのつみたて投資枠のメリット・デメリット

ここからは、新NISAのなかでも、つみたて投資枠を活用することのメリットとデメリットをそれぞれ解説する。
メリットをまとめると、以下のようなものがある。
- 安定した資産形成が可能
- 初心者に適した設計になっている
- 一度設定すれば、その後自動的に買付できる
新NISAで投資できるのは、金融庁の基準をクリアした一定の投資信託と上場投資信託だ。
なかでもインデックスファンドと呼ばれる投資商品は、日経平均株価・TOPIX・S&P500(アメリカ)」などの指数に連動する値動きを目指しており、指数に含まれる全銘柄を、全て同じ比率で投資をするのと同様のリスク分散効果が期待できる。
個別の上場株式に集中投資するのと比較して価格変動リスクが抑えられるため、安定した利益の獲得が狙えるだろう。
また、投資できる商品が厳選されているうえ、一部ネット証券では100円から投資することも可能。
投資に大きな予算を振り向けたり、投資商品を多くの選択肢から厳選したりすることが難しい初心者の方でも取り組みやすい。
購入方法は積立のみなので柔軟な売買はできないが、手続きさえすれば自動的に一定額を投資できるので手間もかからない。
一方、以下のようなデメリットがあることには要注意だ。
- 短期的に大きなリターンを求めるのには向いていない
- 投資対象が限定されている
- 年間の非課税限度額が少なめ
つみたて投資枠で投資できるインデックスファンドなどの商品は、数百~数千銘柄に分散投資できることで個別株式と比べて値動きがマイルドになっている。
大きく値下がりするリスクを抑えられる反面、短期的に大きなリターンを得るのには向いていない。
また投資できる商品は金融庁の基準を満たす一定の投資信託などに限定されているため、商品選択の自由度は低い。
年間で120万円の非課税限度額は成長投資枠の半分であり、短期的に高額の投資はしにくい設計だ。
新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠はどちらを使うべき?

成長投資枠とつみたて投資枠は特徴が異なるため「どの投資枠をメインで利用すれば良いの?」と考えてしまう人も多いだろう。
ここでは、新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠のどちらを利用するべきか、それぞれに向いている人の特徴を解説する。
まとまった投資で利益を狙うなら「成長投資枠」がおすすめ
2つの投資枠のうち、成長投資枠が向いているのは、以下のような特徴を持った人だ。
- 個別株に投資をしたい
- 短期間で大きなリターンを狙いたい
- まとまった資金で運用したい
成長投資枠のメリットは、上場している個別株式に投資できることだ。
分散投資はしにくくなるが、株価が上昇する銘柄に投資できた時は短期間で高額の含み益を得られる可能性がある。
個別株の売買を繰り返すことで短期間にまとまった利益を得ることも可能だろう。
ただ、個別株は100円から投資できる投資信託と比較して購入価格が高くなるため、まとまった資金がある人向けだ。
コツコツと長期投資で利益を狙うなら「つみたて投資枠」がおすすめ
一方、つみたて投資枠が向いているのは以下の特徴に当てはまるケースだ。
- 長期的に資産形成をしたい
- 値動きをマイルドに抑えたい
- 手間をかけずに投資したい
販売手数料がゼロだったり信託報酬が一定水準以下だったりといった基準を満たした投資信託が投資対象で、長期的な資産形成に向いている。
また、投資信託は個別株式よりも分散が効いており、株式100%の投資信託でも少数の個別株式に集中投資するよりは値動きは緩やかだ。
債券に投資できる投資信託をポートフォリオに組み込むことで、さらに値動きを抑えた投資も可能だ。
積立投資は最初に設定すれば手間いらずの投資ができるため、自動的に資産運用を進めたい人もつみたて投資枠を活用しよう。
成長投資枠とつみたて投資枠は併用もおすすめ!
なかには、成長投資枠とつみたて投資枠の両方を併用するほうが良い人もいる。その特徴は以下のとおりだ。
- 片方の投資枠では資金が余ってしまう人
- スポット投資や積立投資について分析する時間がある人
新NISAのメリットの1つに、成長投資枠とつみたて投資枠の併用ができる点がある。
つみたて投資枠の年間投資枠が120万円、成長投資枠は240万円。これだけでも十分な枠だが、併用することで年間最大360万円まで投資できる。
新NISAの非課税限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)と上限が決まっているものの、毎年の投資額を増やせば短期間で枠を使い切って効率的な運用が可能になるだろう。
投資に回せる余剰資金があり、より早く資産形成を進めたい方は2つの枠の両方に可能な限り投資をするのがおすすめだ。
ただし、投資額が増えれば日々の値動きも大きくなり、投資する銘柄の種類が増えれば分析にも時間がかかることになる。
2つの投資枠をフル活用するなら、値動きに耐えられそうか、投資銘柄の分析やそれに伴う取引に十分な時間を確保できるかを事前に考えておこう。
新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠はプロに相談!

枠の使い分けに迷ったときは、以下のような資産運用のプロフェッショナルに相談しよう。
新NISAについて専門家に相談する重要性
新NISAとその投資枠について、専門家に相談するべき理由は、投資枠の違いを理解することで「自分に合う戦略を立てられるようになる」という点が大きい。
資産運用をする際は闇雲に投資先を決めて適当にお金を出すのではなく、自身のライフプラン・ライフステージに合わせて資金計画を立てたうえで、運用の目的や個人ごとのリスク許容度に合うポートフォリオを作成することが重要になる。
ポートフォリオの内容によって、どの枠にどのくらい投資するかが変わってくるため、投資前に方向性を決めておくことは大切だ。
ただ、投資初心者の方が手探りで自分に合うポートフォリオを考えるのは非常に難しく、できたとしても時間と労力がかかってしまう。
長期投資が重要な新NISAにおいて、ポートフォリオ作成に余計な時間をかけることでせっかくの制度の魅力を活用できない可能性すらあるのだ。
そこで、資産運用の専門家に相談することができれば、自分でポートフォリオに悩む手間や時間をかけることなく、自身のリスク許容度に合わせた最適なポートフォリオを作成してくれるだろう。
新NISAについてのおすすめ相談先3選
新NISAについて悩みがある場合のおすすめ相談先3選は、以下のとおりだ。
| おすすめ相談先 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 証券会社 | 投資に関する専門知識を有する 投資商品の種類が多い 独自の相談サービスがある | 一般投資家は相手にされない可能性がある 支店数が少なく対面相談には不向き |
| 銀行 | 新NISAや商品の説明が丁寧 対面でアドバイスをもらえる 口座開設手続きがスムーズ | 手数料がネット証券と比較して高い 銀行のおすすめ商品を紹介される 営業時間内でしか相談できない |
| IFA | 個別銘柄のアドバイスも可能 中立の立場でアドバイスをくれる 販売ノルマがなく余裕のある提案ができる | IFAの数が少なく対応エリアが限定されている 信頼できるIFAを見つけにくい |
証券会社は資産運用の一般的な相談先で、担当者は株式や投資信託の専門知識を有している。
投資商品の種類が多く独自の相談サービスがある一方で、富裕層以外の一般投資家が相談しても相手にされない場合があることに注意してほしい。
銀行は新NISAや商品の説明が丁寧で対面アドバイスがもらえるというメリットがあるものの、手数料がネット証券と比較して高いことなどがデメリットだ。
IFA(Independent Financial Advisor)は特定の金融機関から独立した金融アドバイザーで、中立の立場でアドバイスをしてくれるのが魅力といえる。
また、投資助言・代理業の登録をしているため、個別銘柄に関する助言も可能だ。
ただし、FP(Financial Planner)と比較して数が少なく、信頼できるIFAを見つけるのは一般的に難しい。
適切な相談先を選定するにあたっては、担当者が幅広い金融商品の知識・金融業界での実務経験・コミュニケーション能力を有しているかなどの確認が必要だ。
新NISAに関する悩みがある場合、これらの資産運用アドバイザーに相談して早期に問題解決するのがおすすめといえる。
成長投資枠とつみたて投資枠の主な違いは年間投資枠と非課税保有限度額!
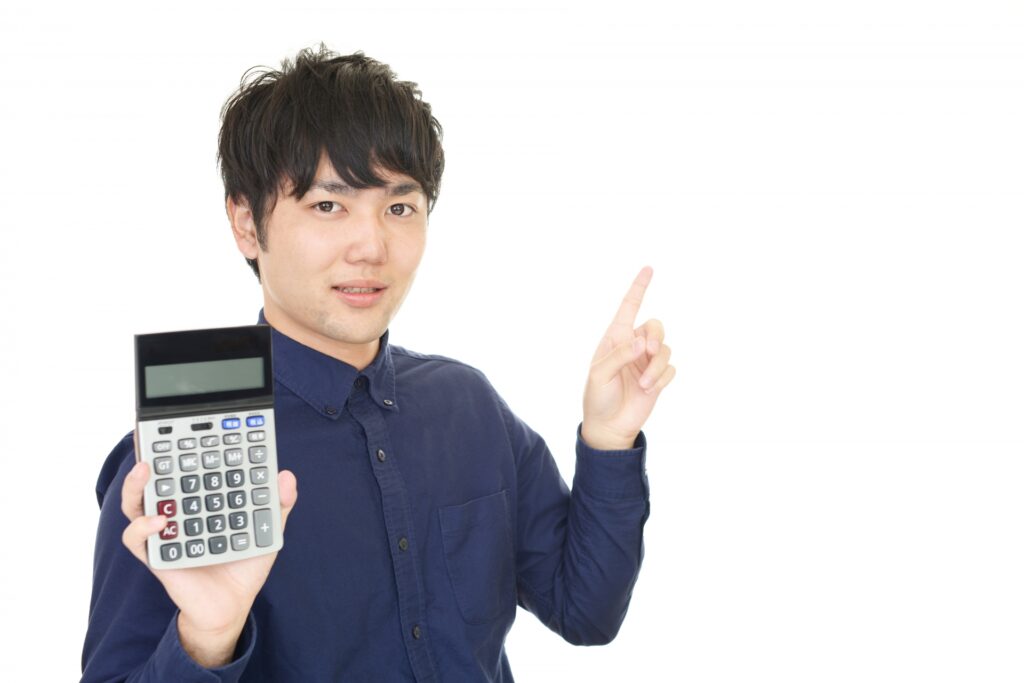
本記事では、新NISAにおける成長投資枠とつみたて投資枠の違いやメリット・デメリットなどについて解説した。
2つの投資枠の主な違いは、年間投資枠と非課税保有限度額だ。
成長投資枠の年間投資枠は240万円・つみたて投資枠では120万円に設定されている。
前者は余剰資金を自由に投資したい場合に、後者は毎月積立などでコツコツ行いたい場合におすすめだ。
また、2つの投資枠は併用できるため、ぜひ目的に応じて使い分けてほしい。
とはいえ、新NISAの活用を含めて投資をしたいと思っても、悩ましいことは次々と発生するだろう。
新NISA関係で悩んだら資産運用のプロへ早めに相談し、効率的な投資を行おう。
成長投資枠とつみたて投資枠の違いに関するよくある質問