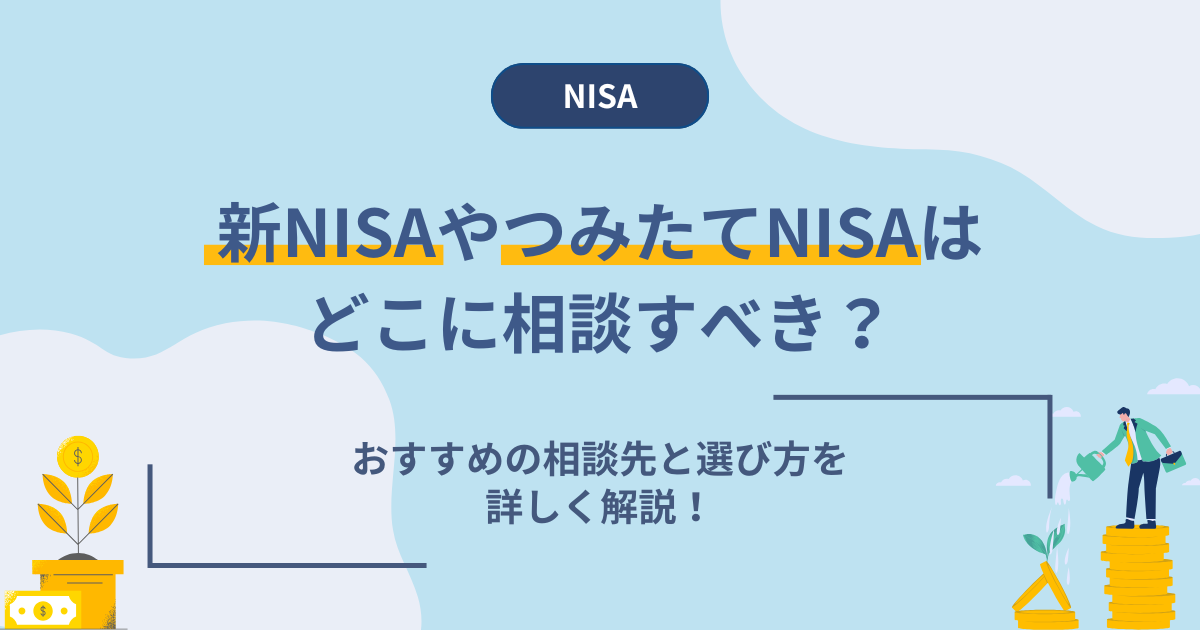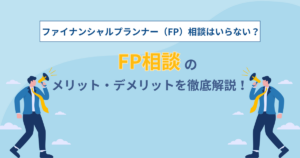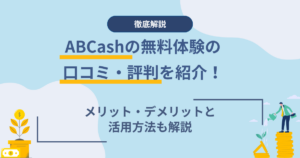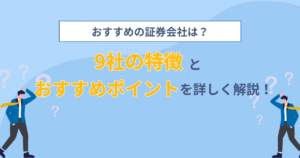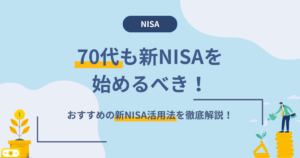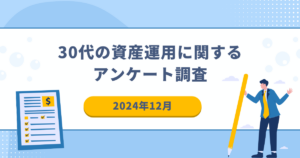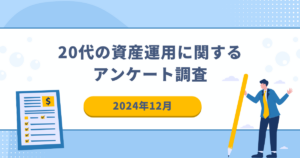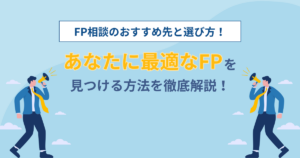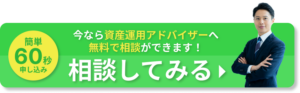- 初心者でも相談できる新NISAの相談先が知りたい
- 新NISAの相談先を選ぶときにチェックすべきポイントが知りたい
- 新NISAの相談前に準備すべきことが知りたい
これから新NISAで積立投資に挑戦したいという人も多いのではないだろうか。
新NISAは資産運用で得られた売却益や配当金・分配金が非課税になる制度だ。
2024年以降、新制度に移行して旧制度の「つみたてNISA」の役割は新制度の「つみたて投資枠」が引き継ぐ形となった。
非課税保有期間が無期限になったり、年間に投資できる枠も増えたりと使い勝手が良くなった。
このような背景もあり注目されている新NISAではあるが、運用方針に悩んでいて上手く活用できていなかったり始められなかったりする人もいることだろう。
そこで頼ってほしいのが資産運用のプロだ。本記事では新NISAの相談先の選び方や探し方について解説する。
初心者にもおすすめ!新NISA(旧つみたてNISA)の相談先3選

新NISAの積立投資をどこで相談するかで悩む人も多いだろう。注意したいのがNISAの口座は複数の金融機関に同時に持つことができない点だ。
1人1口座までしか持てず運用する口座を変更する場合は少々、面倒な移管手続きをしなければならない。
そのため、相談と運用を兼ねている金融機関に口座開設する場合は慎重に選んでほしい。
まずは、新NISAの相談先の代表として考えられる以下の3つの特徴を解説する。
- 銀行
- 証券会社
- IFA
それぞれ、どこが自分と相性が良さそうかを確認してほしい。
銀行:普段利用しているところなら相談しやすい!
- 普段、利用している銀行なら口座開設や相談がしやすい
- 投資できる商品の数や種類が少ない可能性もあるため事前に確認がおすすめ
- 積立投資したい投資信託の取り扱いがあり、個別株投資をする予定がない人におすすめ
- 提案が営業方針に縛られることもある
普段、利用している銀行でも新NISAの相談は可能だ。店頭で新NISAの口座開設の案内を目にしたり、勧誘をされたりした経験がある人も多いのではないだろうか。
特に店舗が生活圏内にあったり、普段から利用していたりすれば相談しやすいという安心感があるだろう。
ただし、銀行でNISA口座を開く際に注意したいのが投資できる商品の幅が少ない点だ。
新NISAのつみたて投資枠の投資対象は金融庁が認めた「長期・積立・分散投資に適した投資信託」に限られている。
このルールは全ての金融機関のNISA口座に当てはまる。注意したいのは各金融機関で取り扱っている投資信託の数や種類が違う点だ。
相談だけでなく実際に銀行口座で新NISAの積立投資をする場合、取扱商品の数と種類に注目してほしい。
大手ネット証券が200以上のラインナップをつみたて投資枠で投資できるのに対して、多くの銀行で取り扱っている商品数は程度の差はあれど限られているのが現状だ。
つみたて投資の基本は同じ投資信託を継続的に買い続けることなので、投資対象として納得できる投資信託の取り扱いがあれば、それほど気にならないかもしれない。
しかし、選択肢が少ないことで投資信託を妥協してしまうことにならないように注意してほしい。
また、新NISAのつみたて投資枠は、投資信託のみしか取引できないが、成長投資枠に関しては個別株投資もできる。
しかし、銀行はそもそも個別株の取り扱いをしていないため銀行口座で新NISAを運用する場合、成長投資枠での個別株投資の選択肢を捨てることになる点にも注意しよう。
そして銀行に限らない話だが、銀行のアドバイザーは所属している金融機関の営業方針に縛られやすい立場にある。
そのため、提案が本当に顧客本位の納得できる内容となっているかどうかを気にしておく必要があるだろう。
証券会社(対面):成長投資枠で個別株投資にも挑戦できる!
- 幅広い金融分野の中でも証券会社は特に資産運用のプロ
- 成長投資枠を利用する場合、個別株投資にも対応できる
- 証券会社の窓口で相談するのは人によっては気後れしてしまうことも
- 提案が営業方針に縛られることもある
証券会社でも対面証券ならプロに新NISAの相談ができる。
対面証券の強みはなんと言っても、幅広い金融分野の中でも資産運用や投資に対する知見やノウハウの点で信頼感があるところだろう。
特に銀行との違いは成長投資枠で個別株の取り扱いもできる点だ。投資信託の積立だけでなくNISAで個別株の運用も取り入れたいという場合は証券会社がおすすめだ。
ただ、銀行に比べると対面証券の窓口を訪れて新NISAの相談をするのは、人によっては少し気後れしてしまうこともあるかもしれない。
また、対面証券の場合、新NISAのつみたて投資枠の取扱商品に関しては、会社によって商品ラインナップに差がある。
対面証券の中には新NISAで選べる取扱商品が少ないところもあるため、事前に確認しておくことをおすすめする。
また、銀行同様、証券会社のアドバイザーも所属先の営業方針に縛られやすい立場にある。
そのため、提案された内容が本当に顧客本位かどうかをご自身で判断する必要があるだろう。
IFA:大手ネット証券と提携しているIFAもあり!
- 顧客本位の提案をしやすい立場に期待できる
- 大手ネット証券と提携しているIFAは商品の幅が広い
- IFAによって営業方針や専門性など違いは大きい
IFAとは独立系ファイナンシャルアドバイザー、金融商品仲介業者のことだ。
特定の金融機関ではなくIFA法人に属しておりノルマに縛られずに顧客本位の提案をしやすい立場にある。
IFAのアドバイザーは証券会社をはじめとした金融機関出身が多い。そのため、プロの知見、提案を期待できる。
またIFAは金融商品仲介業なので各種金融機関と提携している。例えば、大手ネット証券のSBI証券や楽天証券などと提携しているIFAも多い。
大手ネット証券の持つ幅広い商品ラインナップの中から、IFAが顧客本位の立場でプロの知見をもとに提案できる点が強みと言えるだろう。
ただし、IFAと言っても実に多様だ。営業方針や専門性などIFA法人とアドバイザーによって様々だ。
そのためIFAに相談する際には、IFAとの営業方針や相性などをよく確認する必要があるだろう。
新NISAの相談先を選ぶときにチェックするポイント
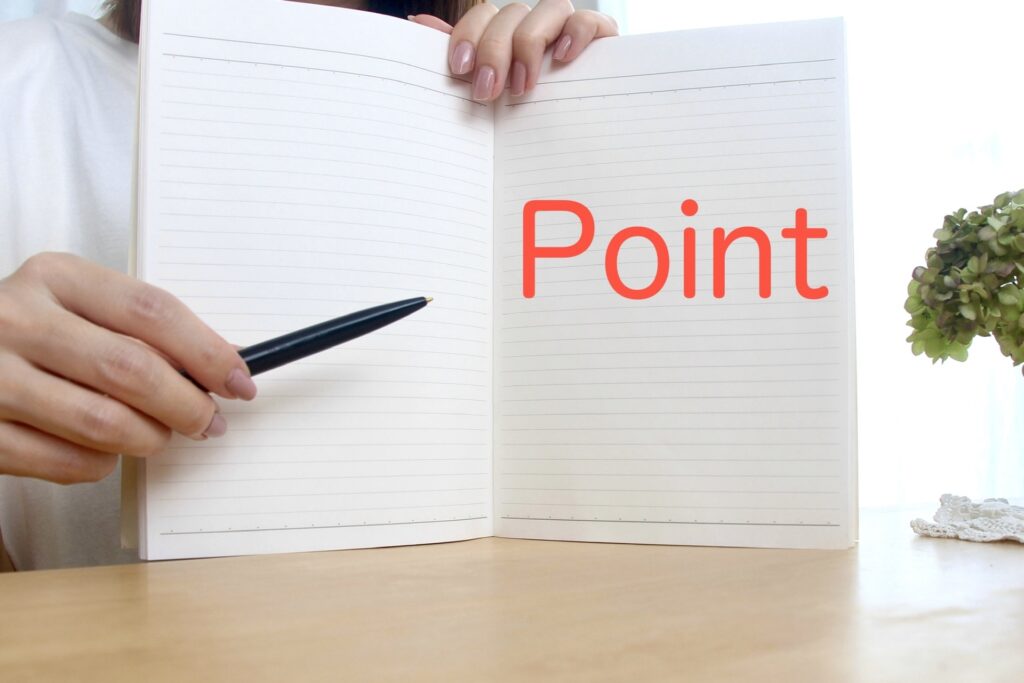
新NISAの相談先を選ぶ際にチェックしてほしいポイントが4つある。
- 相談内容に適しているかどうか
- 初心者でも相談しやすいか
- 手数料がわかりやすいかどうか
- 長期的なサポートはあるかどうか
それぞれ確認してみよう。
相談内容に適しているかどうか
まずは、相談内容と相談先の対応業務が対応しているかどうかを確認しよう。
例えば、個別具体的な商品の提案や仲介を希望しているのに対応業務ではない独立系FPに相談してしまうとミスマッチになってしまう。
つみたて投資枠とあわせて成長投資枠で個別株投資を相談したいのに、個別株の扱いがない銀行に相談をしても対応してもらえない。
資産運用のプロと言ってもそれぞれ得意分野や専門領域がある。そのため、自分の相談したい内容が対象業務なのかどうかは事前に確認しておこう。
初心者でも相談しやすいか
特に初心者なら、投資未経験でも相談しやすいかどうかも重要なポイントだ。
相談先の中には、初心者お断りのような雰囲気のところ、相談しても初心者に寄り添った分かりやすい説明や提案をしてもらえなかったりすることもあるかもしれない。
もし相談しにくい雰囲気だったり、説明や提案が分かりづらいと感じたりしても引け目に感じることはない。
そのような相性の悪い相談先では今後、新NISAでの運用を長期的に続けていきづらいだろう。相談しやすく分かりやすい説明がなければ、納得感のある投資は難しい。
仮に取扱商品が豊富でなかったり、専門性がそこまで深くなかったりしても初心者に寄り添ってくれる相談先やアドバイザーの方が結果的に納得できる投資ができる可能性もある。
手数料がわかりやすいかどうか
手数料の透明性やわかりやすさに関しても確認しよう。
手数料が不明瞭な相談先でよく確認せずに口座を開設し取引をしてしまうと様々な場面で想定外の手数料を負担しなければいけなくなる。
口座維持や売買手数料、投資信託を保有するコストなど事前に明確にしておくことをおすすめする。
はぐらかせたり、誤魔化されたり、手数料に関する十分な説明がない相談先は避けたほうが無難だろう。
長期的なサポートはあるかどうか
新NISAでも特につみたて投資枠は「長期・積立・分散」が推奨されている。
新NISAは短期間の投資ではなく長期的な資産運用のために利用するのが前提だ。そのため、長期的なサポートを期待できそうかどうかも相談先選びのポイントだ。
一度、投資する商品を決めてしまえば、後は機械的に積立するだけでサポートは必要なのかと疑問に思うかもしれない。
しかし、長期的に投資を続けていくとポートフォリオのリバランス、運用先と戦略の見直しが必要になったりすることも考えられる。
資産を長い目で育てていくためにも長期的なサポートを期待できる相談先が望ましい。
新NISAの相談NG!避けた方がよい相談先を解説

新NISAの相談先を選ぶ際には、相談内容に見合った専門性を持つ窓口を選ぶのがポイントだ。
誰に相談しても同じではなく、業態によって提供できるアドバイスの範囲や内容は大きく異なる。
ここでは投資を失敗しないために、新NISAの相談先として避けた方がよい相談窓口について解説しよう。
FP:具体的な銘柄相談ができない!
FPとは、家計の収支管理や資産設計、保険や税金など幅広い金融知識をもとにライフプランに沿った資産形成をサポートする専門家のこと。
しかし、実はFPの多くは具体的な金融商品の仲介・販売ができる資格を持っていない。
FPの主な業務は以下のような内容に限られることが多い。
- ライフプランの設計と資金計画
- 老後資金の試算とアドバイス
- 家計の収支分析
- 保険の見直し
- 相続対策
たとえば「将来の教育資金としてどのくらい資産形成が必要か」「老後の生活費はいくら必要か」といった包括的な資金計画の相談はできる。
一方で「どの投資信託を買うべきか」「この株は買いか」といった具体的な商品の推奨はできないのだ。
また、FPの資格は比較的取得しやすく、3級であれば1ヶ月〜数ヶ月程度の勉強で取得可能だ。そのため、金融知識や投資経験が浅いFPも少なくない。
もし相談するなら、金融機関での実務経験があるか、1級FP技能士など上位資格保有者を選んだ方が質の高いアドバイスを期待できるだろう。
具体的な投資戦略や銘柄選択まで含めた相談がしたいなら、証券会社やIFAなどを選ぶべきだ。
保険会社:あくまで「保険相談」がメインになる!
保険会社の社員や代理店は、基本的に保険商品の販売がメインの業務となっている。
たしかに保険の中にも「変額保険」や「外貨建て保険」など運用要素を含む商品は存在するが、これらは投資信託や株式とは異なるものだ。
保険会社への新NISA相談には、以下のようなデメリットがある。
- 投資信託よりも外貨建て保険などの保険商品を勧められる可能性が高い
- 保険契約を契約を取ることが優先されるので、新NISA口座での運用と比較した場合のメリット・デメリットの説明が不十分になる(※一般的に、得られる利益だけ比較すると自分で新NISA口座へ投資する方が得をする)
- 証券外務員資格がない担当者だと運用商品の提案ができない
保険商品の年間手数料(コスト)は投資信託と比べて高くなる傾向にある。
投資信託の信託報酬が年0.5〜2%程度となるケースが多いのに対し、外貨建て保険などの運用コストは年2〜5%に達することも珍しくない。
そしてこの差は、運用期間が長いほど大きくなってしまう。
また、保険会社の担当者は保険販売のノルマを持っていることが多い。相談者の最適な資産運用よりも、自社の保険商品販売を優先する可能性もあるのだ
もし保険と投資を組み合わせたい場合は、まず投資専門の相談先であるIFAや証券会社に、新NISAについて相談しよう。
医療保障・死亡保障など保障が必要な部分は、別途保険会社に相談するのがおすすめだ。
新NISAの相談前をスムーズに進めるコツ

何も準備せずに相談をしてしまうと伝えるべきことが上手く伝わらないだろう。
新NISAの相談をする前に事前に以下の3つを準備しておくと、スムーズに話が進められる。
- 新NISAの基本を確認する
- 現在の収支を整理する
- 運用目標を考える
新NISAの基本を確認する
まず新NISAの基本的なルールを確認しておこう。概要は以下の通り。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円ただし成長投資枠の上限は1,200万円まで | |
| 投資対象 | 上場株式、投資信託など ※一部のリスクの高い銘柄などは除く | 長期・積立・分散投資に適した金融庁の基準を満たした投資信託 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
注意点としては、年間投資枠は一度、売買してしまうと再利用はできない。また、NISA以外の特定口座や一般口座との損益通算もできない点も確認しておこう。
新NISAで運用する金額を決める
続いて、現在の収支状況をもとに新NISAの運用額をざっくりと決めてみよう。
やみくもに投資するのではなく、自分の経済状況に見合った金額設定が長期的な成功につながるからだ。
また、無理をして投資に回すと、物価の上昇やボーナスの減少で生活が破綻してしまうリスクもある。
以下の4ステップで、運用に回す金額を決めていこう。
- 月々の収入を把握する(手取り給与、副収入など)
- 固定費を洗い出す(家賃、光熱費、通信費、保険料など)
- 変動費を見積もる(食費、交際費、趣味娯楽費など)
- 収入から固定費と変動費を引いた余剰資金を算出する
この余剰資金の中から、どれくらいを投資に回せるかを判断する。
ただし、投資に回す前に、まずは緊急資金として3〜6か月分の生活費は別途確保しておくのがよい。急な出費や収入減少に備えるためだ。
なお、新NISAは「つみたて投資枠」を活かした、毎月一定額を投資する「定額積立」が基本。
しかし「成長投資枠」を使えば、ボーナス月に増額したり、収入に応じて柔軟に金額を調整したりする方法も可能だ。
つみたて投資枠も成長投資枠も非課税期間は無期限のため、最初に決めた金額をベースに「無理のない金額」に調整しながら続けていくのがよいだろう。
運用目標を考える
新NISAでどの程度の運用リターンを目標にするかも自分なりに考えてみよう。仮に実現が難しかったり、見当はずれだったりしても構わない。
自分なりの仮説や目標を踏まえてプロのアドバイザーに相談した方が結果、納得できる運用につながるはずだ。
例えば、このリターンを目標にするなら、この程度のリスクを取らなければいけない等、より具体的なアドバイスをしてもらえるだろう。
信頼できるプロに相談して新NISAを成功させよう

本記事で紹介したように、銀行や証券会社、IFAなどさまざまな相談先がある。自分の状況や目的に合った窓口を選ぶのが成功のポイントだ。
- 銀行
- 普段利用している銀行なら相談しやすく、投資信託の積立が主な目的なら選択肢になる
- 証券会社(対面)
- 資産運用のプロとして幅広い知識を持ち、個別株投資も含めた提案ができる
- IFA
- 特定の金融機関に縛られず、顧客本位の提案を期待できる
一方で、以下のような相談先は避けた方がよいかもしれない。
- FP
- 全般的な資産設計はできるが、具体的な銘柄提案はできないことが多い
- 保険会社
- 保険商品の提案がメインとなり、新NISAに適した投資提案が期待できない
相談前には新NISAの基本を理解し、自分の収支状況を把握したうえで運用可能な金額を決めておけば、より効果的な相談が可能になる。
毎月の積立額は無理なく継続できる金額に設定し、長期的な資産形成を目指そう。
2024年から始まった新NISAは、非課税保有期間が無期限になるなど、より長期投資に有利な制度となった。
早めに新NISAをはじめるほど、得られる恩恵は大きくなりやすい。さっそくプロに相談して、自分に合った投資スタイルを確かめてみよう。